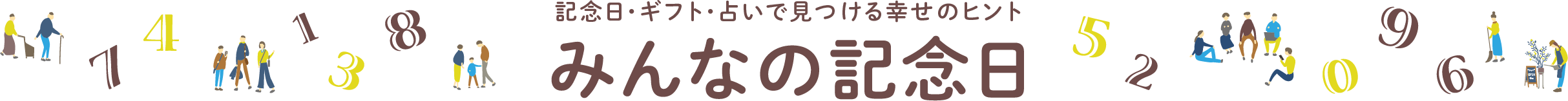立夏(りっか)の季節がやってきました。
風が心地よく、陽ざしに初夏の気配が感じられるこの時期、自然界は一層いきいきと動きはじめます。
2025年の立夏は【5月5日】。例年と同じく5月5日頃から5月20日頃までが「立夏」の期間にあたりますが、二十四節気は太陽の動きに基づいて決まるため、年によって日付は前後します。
ゴールデンウィークの終盤と重なるこの季節は、気温も安定しはじめ、外に出て季節を楽しむにはぴったりの時期。この記事では、そんな「立夏」の意味や自然の変化、暮らしに取り入れたいポイントについて詳しくご紹介します。
二十四節気(にじゅうしせっき)は、太陽の動きに基づいた中国起源の暦です。1年を24等分し、各節気は約15日間隔で巡ります。節気には、気候の特徴や農作業の目安が示され、自然のリズムを感じながら生活をする知恵が伝わっています。
立夏の七十二候とは?意味と時期、季節の移ろいをわかりやすく解説
立夏の期間には、以下の三つの七十二候があります。
- 初候:蛙始鳴(かわずはじめてなく)
- 期間:5月5日頃から5月9日頃
- 意味:田んぼに水が引かれる時期で、蛙が鳴き始める時期です。田んぼや池から蛙の鳴き声が聞こえ始め、それが夏の訪れを実感させます。
- 次候:蚯蚓出(みみずいづる)
- 期間:5月10日頃から5月14日頃
- 意味:蚯蚓(みみず)が地上に出てくる時期です。地面のなかも温まり、蚯蚓の活動が活発になり始めます。
- 末候:竹笋生(たけのこしょうず)
- 期間:5月15日頃から5月20日頃
- 意味:竹林では筍が顔を出します。筍の成長はとてもはやいもの! その早さに驚かされます。
七十二候は季節の微妙な移り変わりを表し、自然のリズムを感じることができる日本独特の文化です。詳しい記事は、下のリンクからどうぞ。
二十四節気のひとつ「立夏(りっか)」とは、夏の始まりを知らせる節気のこと
立夏は、夏の訪れを告げる重要な節気であり、日本の自然や文化に深く根ざしています。
立夏とは、簡単にいうと、夏の始まりを示す節気のことです。
この頃は、自然の変化を感じながら、春から夏への移り変わりを楽しむ時季です。4月末から5月頭のゴールデンウィークには、みどりの日や、憲法記念日、端午の節句などの祝日がありますが、中でも端午の節句は、こどもの成長を祝う大切な日です。
また、旬を迎える食材も増え始めます。
竹笋生(たけのこしょうず)についてちょっと詳しく
末候:竹笋生(たけのこしょうず) とは、「たけのこが生えてくる」という意味です。たけのこが地面から顔を出し、勢いよく成長を始める様子を表しています。
まさしく旬! 地面から顔を出したばかりのたけのこが収穫されます。収穫時期が限られているため、この時期にしか味わえない新芽の柔らかさと香りが堪能できます。
竹の成長力は非常に旺盛で、1日で数十センチ伸びることも珍しくありません。この時期になると、たけのこが竹林で次々と顔を出し、初夏の陽気の中でぐんぐんと成長します。
筍は収穫後すぐにアクが強くなるため、早めに処理しましょう。茹でてアク抜きした後は、冷蔵庫で保存するか、冷凍保存することで長持ちします。筍は収穫後できるだけ早く調理することで、その美味しさを最大限に楽しむことができます。
立夏の風物詩|初夏の訪れを感じる自然と暮らし
毎年5月5日に祝われる日本の伝統的な行事で、五節句の一つです。主に男の子の健やかな成長と健康を願う日として知られていますが、元々は厄除けや農耕儀礼に由来する節句です。
端午の節句の由来とは?|男の子の健やかな成長を願う日
「端」は始まり、「午(ご)」は十二支の「午(うま)」を指します。古代中国では、五月は厄を祓う月とされ、午の日に邪気払いの行事が行われていました。それが日本に伝わり、5月5日が特定の日となりました。
鯉のぼりとは?|立夏の空に泳ぐ、子どもの健やかな成長の象徴
鯉のぼりは、端午の節句(5月5日)に掲げられる飾りで、もともとは武家社会で始まりました。
中国の古い故事「登竜門(とうりゅうもん)」に由来しており、「鯉が急流をのぼって龍になる」という伝説から、どんな困難にも負けず、立派に成長してほしいという願いが込められています。
この伝説は、「努力すれば出世できる」という意味を持ち、特に男の子のたくましさと将来の成功を願って、江戸時代には武家から町人へと広まりました。
鯉のぼりに込められた意味
鯉のぼりには、以下のような願いが込められています。
- 健やかな成長
風にたくましく泳ぐ鯉の姿は、子どもがのびのびと健やかに育ってほしいという願いの象徴です。 - 出世と成功
鯉が滝を登りきって龍になるという中国の伝説「登竜門」にちなみ、困難を乗り越えて立派に成長し、成功をおさめてほしいという思いが込められています。 - 家族の繁栄
黒い鯉は父、赤い鯉は母、青や緑の鯉は子どもを表し、それぞれの鯉が家族を象徴しています。鯉のぼりを掲げることは、家族みんなの健康と幸せを願うしるしでもあります。
鯉のぼりの構成と意味
一般的な鯉のぼりは、以下のような順に飾られます
① 吹き流し(ふきながし)
意味:邪気を払う魔除け
五色(青・赤・黄・白・黒)で構成され、中国の五行思想(木火土金水)に基づく色です。鯉のぼりの一番上で風になびき、運気を呼び込み、災いを遠ざけるとされています。
② 矢車(やぐるま)
意味:風向きや風の強さを表す道具
風を受けてカラカラと回る音は、悪霊を追い払うともいわれ、音による魔除けの役割も担っています。
③ 鯉のぼり本体(鯉の形をした吹き流し)
子どもの人数に合わせて鯉が増えることもあります。
家族を象徴する鯉たちで、上から順に
真鯉(まごい)=黒 → 父
緋鯉(ひごい)=赤(またはピンク)→ 母
子鯉=(青・緑・オレンジなど)→ 子どもたち
④ ポール(支柱)
鯉のぼり全体を支える柱。昔は高く立てて目立たせていましたが、
近年ではベランダ用・室内用の小型タイプも人気です。
まとめ
いかがでしたか?
端午の節句は、もともと男の子の健やかな成長を願う行事として受け継がれてきましたが、最近ではジェンダーにこだわらず、「こどもの日」としてすべての子どもたちの幸せを願う日として親しまれています。住宅事情などもあり、空を泳ぐ鯉のぼりを見る機会は少なくなってきましたが、季節の風物詩として、これからも大切にしていきたい日本の文化ですね。
季節のうつろいに目を向けるだけで、なんとなく気持ちが整うことってありますよね。今年の5月5日は、日本の伝統にふれて、ほんの少し豊かな時間を過ごしてみませんか?
次回は、小満(しょうまん)についてご案内します。小満は、小さい満足の意味もあるのですが、どんな満足なのでしょうか? 紐解いていきます。