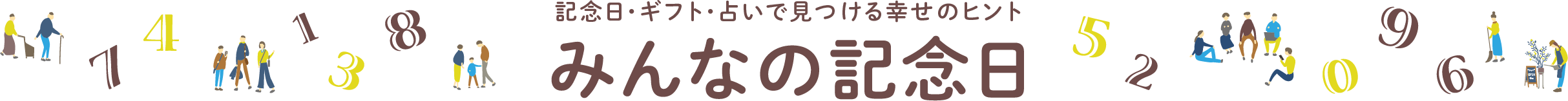小暑(しょうしょ)は、本格的な夏の暑さが始まる頃を指しています。暑さが徐々に増していく時季です。
二十四節気・小暑とは、夏の気配が、ぐっと近づいてくるころ
「小暑(しょうしょ)」とは、文字どおり“ちいさな暑さ”という意味。
本格的な夏の前触れのようなこの時季は、まだどこか梅雨の名残もありながら、少しずつ空気が夏へと切り替わっていく時期です。
毎年7月7日ごろ、小暑を迎えるころになると、
セミの声が聞こえ始めたり、朝夕の風に夏の匂いが混じったり──
自然の中に「夏がくるよ」とささやくサインがあちこちにあらわれてきます。
梅雨明けも近づき、空が明るく感じられるようになる頃。
これからやってくる暑さに向けて、心と身体の準備を整える、そんな節目のような日です。
二十四節気(にじゅうしせっき)は、太陽の動きに基づいた中国起源の暦です。1年を24等分し、各節気は約15日間隔で巡ります。節気には、気候の特徴や農作業の目安が示され、自然のリズムを感じながら生活をする知恵が伝わっています。
小暑の期間に含まれる七十二候とは?
小暑の時期には、「七十二候(しちじゅうにこう)」と呼ばれる、自然の変化をさらに細かくとらえた暦が登場します。
七十二候とは、一年を72の小さな季節に分け、それぞれに名前をつけたもの。
「空気が変わってきたな」「虫の声が聞こえ始めたな」──そんな自然のささやきを感じ取る、日本ならではのやさしい季節のとらえ方です。
小暑の頃にあたる三つの七十二候にも、夏を迎える前の風景が、そっと描かれています。
- 初候:温風至(あつかぜいたる)
- 期間:7月7日頃~7月11日頃
- 意味:暖かい風が吹き始め、夏の訪れを感じさせる時期です。
温風とは、(うんぷう)とも(おんぷう)とも言われます。真夏から夏の末頃まで吹く暖かい風のことを言います
- 次候:蓮始開(はすはじめてひらく)
- 期間:7月12日頃~7月16日頃
- 意味:蓮の花が咲き始める時季です。蓮の花は夏の象徴ともいえる美しい花で、涼しげな景色を作り出します。
- 末候:鷹乃学習(たかすなわちがくしゅうす)
- 期間:7月17日頃~7月21日頃
- 意味:5月〜6月にかけて孵化した鷹のヒナが、飛び方を覚え、昆虫や鳥類が多く見られ始めるこの時期に、狩りを学びます。少しづつ行動範囲を広げつつ独り立ちに備える時季です。
七十二候は季節の微妙な移り変わりを表し、自然のリズムを感じることができる日本独特の文化です。詳しい記事は、下のリンクからどうぞ。
宗教的に重要視される「蓮」と芸術家に好まれる「睡蓮」
次候:蓮始開(はすはじめてひらく)にも出てくる蓮の花。蓮(はす)と睡蓮(すいれん)の見分け方を知っていますか? 昔から混同されることが多いこの植物。どちらも、水辺で見られる美しい花として知られていますが、蓮と睡蓮の違いについて詳しく説明します。
蓮(はす)Lotus の特徴
- 葉の形状: 蓮の葉は大きくて丸い形をしており、葉柄(ようへい)が長く、水面から高く立ち上がります。葉の表面は撥水性があり、水をはじきます。
- 花の特徴: 蓮の花は大きくて華やかで、ピンクや白の花を咲かせます。花も水面から高く伸びる茎の先に咲きます。
- 生息地: 蓮は泥の中に根を張り、湖沼や池などの静かな水辺に生育します。
- 開花時期: 夏(7月から8月頃)
- 文化的意義: 蓮は仏教やヒンドゥー教において神聖な花とされ、仏像の台座などに使われることがあります。
睡蓮(すいれん)Water Lily の特徴
- 葉の形状 睡蓮の葉は蓮に比べて小さく、丸い形をしていて水面に浮かぶように広がります。葉には切れ込みがあります。
- 花の特徴 睡蓮の花も美しいですが、蓮よりも小さく、白、ピンク、黄色、青などさまざまな色があります。花は水面近くに咲きます。
- 生息地 睡蓮も湖沼や池などの静かな水辺に生育します。葉や花は水面に浮かぶ形で成長します。
- 開花時期: 初夏から秋(6月から9月頃)
- 文化的意義: 睡蓮は「水面の宝石」とも呼ばれ、西洋絵画やガーデニングでよく見られます。
蓮と睡蓮の主な違い
下の表に示したように、蓮と睡蓮は見た目や生態が異なりそれぞれ違う特性を持っています。水面から高く立ち上がっているのが、蓮、水面に浮かんで咲いているのが睡蓮。そう覚えると間違いないです。
| 蓮 | 睡蓮 | |
| 葉の位置 | 水面から高く立ち上がっている | 水面に浮かぶ |
| 花の位置 | 水面から高く伸びている | 水面近くに咲く |
| 葉の形状 | 大きく撥水性がある | 小さくて水面に浮かぶ |
| 花のサイズと色 | 大きく主にピンクや白 | 多彩な色 |
| 文化的意義 | 蓮は主に宗教的に重要視 | 睡蓮は主に芸術や園芸で人気 |
七十二候を知ってから、以前にもまして、日本の植物に興味が湧いてくるようになりました。季節の移り変わりと人間の営みがマッチしていると日々の暮らしも気持ちがいいものです。この日本の素晴らしい暦、大切にしていきたいですね。
小暑のころ、夏の気配にふれる
梅雨の終わりが近づくころ、ふと空を見上げたとき、雲が少しだけ夏のかたちをしていた。そんな小さな気づきが、「小暑」の季節の合図かもしれません。朝顔がつるを伸ばしはじめ、ひまわりがまだ頼りなげに陽を追いかける。風鈴が軒先でちりんと鳴って、通りすがりの風の存在をそっと知らせてくれる。うちわの風や、蚊取り線香の香り。かつての夏は、どこか時間がゆっくり流れていた気がします。
最近はミニ扇風機を片手に歩く人の姿が日常になり、日傘や冷却グッズが手放せない季節になりました。七夕や祇園祭、海開きなど、夏の行事は変わらずやってきますが、「夕方になれば涼しくなる」という感覚は、もう過去のものなのかもしれません。夜になっても熱がこもり、エアコンなしでは眠れない夜が続きます。
小暑とは、本来、夏の入口を知らせる、やさしい節気でした。でも今は、暑さとの付き合い方を考える、ひとつの節目のようにも感じます。季節とたたかうのではなく、調和するように暮らすこと。そのヒントは、昔の人が残してくれた知恵の中に、ちゃんと息づいている気がします。
まとめ
小暑は、ただ暑さの始まりを告げるだけの節気ではありません。
それは、夏という季節と、どう向き合っていくかを静かに教えてくれる時間でもあります。
自然のリズムに耳をすませながら、自分のからだや暮らしにもそっと目を向けてみる。
無理せず、でも楽しみながら。
小暑のころの過ごし方が、これから続く夏をやさしくしてくれるかもしれません。
いよいよ夏本番! 次回は、大暑(たいしょ)ついてご案内します。