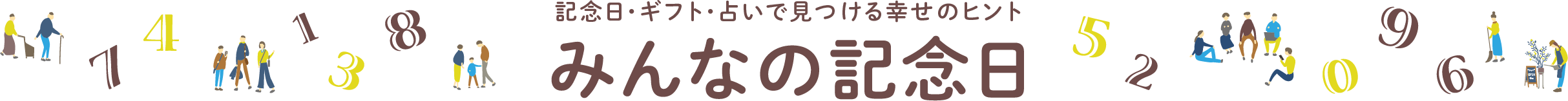「寒」は寒さ、「露」は露を意味し、秋が深まり、朝晩の冷え込みが厳しくなり、草木に冷たい露が降りる頃という意味があります。寒露(かんろ)は、毎年10月8日頃にあたります。
二十四節気・寒露(かんろ)とは、露が降り始める節気のこと
露が冷たく感じるようになり、秋の深まりが感じられる、まさに「寒露」の名にふさわしい時季です。
寒露とは、簡単にいうと、冷たい露が降り始める節気です。
秋がさらに深まり、野生の動物たちの動きが活発になる頃です。渡り鳥は越冬のため、北へ向かいます。またリスなどの小動物たちは、冬を越すため、木の実や植物の種などを蓄えます。この頃には朝晩の冷え込みが本格化し、草木に露が降りやすくなる季節です。
二十四節気(にじゅうしせっき)は、太陽の動きに基づいた中国起源の暦です。
1年を24等分し、各節気は約15日間隔で巡ります。節気には、気候の特徴や農作業の目安が示され、自然のリズムを感じながら生活をする知恵が伝わっています。
寒露の期間に含まれる七十二候とは?
寒露の期間には、三つの七十二候があります。七十二候とは、季節をさらに細かく分けたもので、それぞれの時期に自然界で起こることを表しています。
- 初候:鴻雁来(こうがんきたる)
- 期間:10月8日頃〜10月12日頃
- 意味:寒露の始まりを告げるこの候は、北の国からガンが渡ってくる時季です。この候は、冬鳥の到来を象徴する重要な風物詩です
- 次候:菊花開(きくのはなひらく)
- 期間:10月13日頃〜10月17日頃
- 意味:夏の名残が薄れ、秋の訪れを感じるとともに、菊の花が美しく咲き誇る時期です。古来から、菊は長寿や繁栄の象徴とされ、特別な意味を持っています。
- 末候:蟄虫坏戸(ちっちゅうとをふさぐ)
- 期間:10月18日頃〜10月22日頃
- 意味:コオロギが家の近くで鳴き始める頃。秋の夜長を彩る虫の音が、より身近に感じられるようになります。
次候:菊花開(きくのはなひらく)の如く、寒露の時期に見頃を迎える菊の花ですが、その美しい姿を長く楽しむためには以下のことに注意しましょう。
寒露の時期には、他にも、天皇主催の菊花観賞会や、長崎くんち(長崎県)、伊勢神宮神嘗祭(三重県)など長く続く伝統行事が執り行われます。
伊勢神宮で行われる神嘗祭(かんなめさい)は、新しく収穫されたお米を、天照大御神(あまてらすおおみかみ)にお供えし、今年の収穫に感謝するお祭りです。年間1500回に及ぶ神宮の恒例のお祭りの中でも神嘗祭は特に重要視されています。
また、長崎くんちは、昭和54年には、国指定重要無形民俗文化財に指定されています。
長崎くんちについてちょっと詳しく
毎年10月7日から9日、長崎の街は、異国情緒あふれる熱気に包まれます。国の重要無形民俗文化財にも指定されている「長崎くんち」。今回は、その魅力を分かりやすくご紹介します。
見どころは、なんといっても「奉納踊り」!
祭りの核となるのは「奉納踊」と呼ばれる伝統芸能です。龍踊り、鯨の潮吹き、コッコデショなど、様々な演目が披露されます。これらには、江戸時代に長崎出島を通じて交易のあった中国やオランダの影響が色濃く反映されており、長崎独特の国際色豊かな特徴を持っています。
「よかくんち」の由来とは? 祭りの期間中、地元の人々は「今年のくんちはよかくんちでした」という言葉を交わします。これは祭りの成功を喜び合う伝統的な挨拶です。「よか」には長崎弁で「良い」という意味があり、祭りへの満足感と感謝の気持ちが込められています。
400年以上の歴史と文化が凝縮
長崎くんちは、1634年、二人の遊女が諏訪神社の神様に奉仕を誓ったことが起源とされています。 鎖国時代、唯一の貿易港として栄えた長崎には、様々な文化が流入し、独自の文化が育まれました。 長崎くんちは、その歴史と文化を色濃く反映した祭りといえるでしょう。
長崎くんちは、地域の人々にとって重要な文化イベントであり、長崎の伝統と文化を未来に伝える大切な役割を果たしています。この祭りは、参加する人すべてに喜びと感動をもたらし、毎年多くの人々に長崎の魅力を伝え続けています。
まとめ
いかがでしたか? 寒露は、日本の豊かな季節の移ろいを感じさせる時季であり、自然の恵みへの感謝しつつ、日本の伝統に触れる機会にも多く恵まれる時期です。風物詩を楽しみながら、古(いにしえ)の世に、想いをはせてみるのもよいのではないでしょうか。
次回は、霜降(そうこう)について、ご案内します。