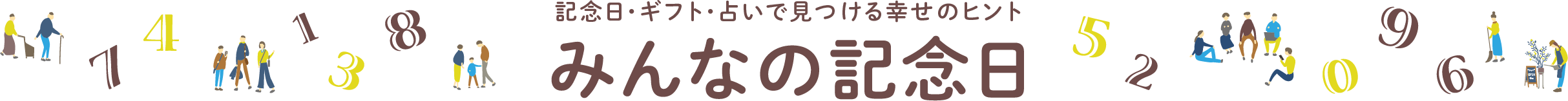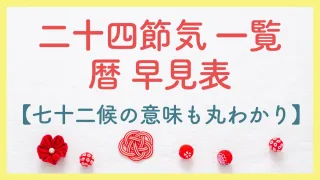七十二候とは?五日ごとの季節を感じる日本の暦
日本の自然は、昔から私たちの暮らしや文化に欠かせない存在でした。なかでも「七十二候(しちじゅうにこう)」は、自然の営みを五日ごとに感じ取る、繊細な暦のことばです。
一見むずかしく感じるかもしれませんが、ひとつひとつを紐解いていくと、自然に寄り添う心のあり方が見えてきます。この記事では、七十二候の意味や背景をたどりながら、日本人が育んできた自然観や、現代に通じる「感じる力」を探っていきます。
↓↓二十四節気早見表はこちらから❤️↓↓
二十四節気と七十二候の違いと関係性をやさしく解説
「七十二候」は、1年を24の節気に分けた「二十四節気」をさらに3つに分け、五日ごとに72の短い期間で構成されています。それぞれの候には、その時期に見られる自然現象や動植物の様子が短い言葉で表現されており、古来より農業や漁業など、自然とともに生きる人々の暮らしを支えてきました。
たとえば「春分」の頃には「雀始巣(すずめはじめてすくう)」、秋の「寒露」には「菊花開(きくのはなひらく)」といった具合に、その季節の変化をやさしく教えてくれるのが七十二候です。
この暦は、ただ時を刻むためのものではなく、自然と調和しながら生きるための“感性のカレンダー”として、私たちの暮らしに深く根ざしてきました。
日本人の自然観と七十二候の背景にある精神性

日本の自然観は、古くから「八百万(やおよろず)の神」に象徴されるように、山、川、風、草木といったあらゆるものに神聖さを見出してきました。この自然崇拝の感覚が、七十二候にも色濃く反映されています。
たとえば「東風解凍(はるかぜこおりをとく)」という表現には、春の風が川辺の氷を静かに溶かしていく情景が詩的に刻まれています。これは単なる気象の記録ではなく、自然への畏敬と感謝が込められた言葉でもあるのです。
こうした候を意識することで、自然の息吹に気づき、私たちの生活にそっと寄り添ってくれる感覚が育まれていきます。
七十二候に描かれる、季節のことばと風景の美しさ

七十二候の魅力は、その表現の美しさにもあります。
「蟄虫啓戸(すごもりのむしとをひらく)」や「雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)」といった表現には、五感を刺激するような詩情があります。こうした言葉に触れると、空の色や風の匂いまでもが立ち上がってくるようです。
また、「桜始開(さくらはじめてひらく)」や「霜始降(しもはじめてふる)」など、季節の風景をそのまま映したような候には、日本人の繊細な感性と自然へのまなざしが表れています。
言葉を通して季節を感じるという、静かで深い文化。それが七十二候です。
暦と行事 ── 七十二候が伝える日本の季節行事とのつながり

日本の伝統行事の多くも、七十二候や二十四節気に根ざしています。
たとえば「立春」は、暦の上での春の始まりであり、節分と合わせて季節の切り替わりを祝う時期です。また「春分」は昼と夜の長さがほぼ等しくなる日であり、お彼岸の行事やお花見のタイミングにも重なります。
「立夏」には端午の節句、「大暑」には土用の丑、「秋分」や「冬至」にはそれぞれ食文化や風習が伴い、七十二候と生活の節目が自然に結びついてきました。
行事を通じて自然とふれあう機会は、現代に生きる私たちにも、季節の移ろいを実感させてくれる大切なひとときです。
現代にこそ取り入れたい、七十二候のある暮らし

都市生活の中では、つい季節の変化を見逃してしまいがちです。けれども、七十二候という暦を通して「今、自然はどんな表情をしているのか?」と問いかけてみるだけで、世界の見え方は変わってきます。
朝の空気のにおい、道端の草の伸び方、鳥の声、夕暮れの色── それらに意識を向けるだけで、私たちは自然と再びつながることができるのです。
七十二候は、自然を「感じる心」を取り戻すきっかけを与えてくれる暦です。
まとめ|七十二候で自然と心が調和する生き方へ
知れば知るほど、その奥深さに惹かれる七十二候。自然のリズムに寄り添い、季節の変化を丁寧に味わうことは、現代においても私たちの心をやわらかく解きほぐしてくれます。
五日ごとの小さな季節のことばを、ぜひ日々の暮らしのなかで感じてみてください。その一言が、あなたの一日に、彩りを添えてくれるかもしれません。