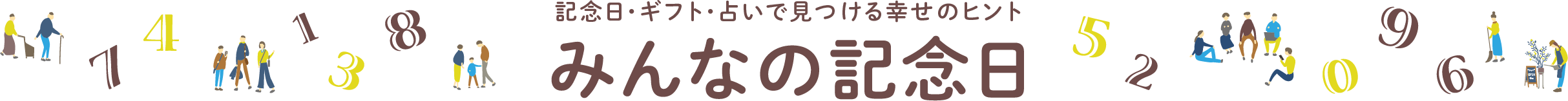大暑(たいしょ)は二十四節気の一つで、毎年7月23日頃にあたります。この時季は、一年で最も暑い時季とされ、夏の真っ盛りを迎えます。今回は大暑についてご紹介します。
二十四節気・大暑のころ、夏のピークを感じて
「大暑(たいしょ)」は、文字どおり“とても暑い”という意味。まさに夏の暑さが極まるころです。空には大きな入道雲がもくもくと湧き、朝からセミの声がにぎやかに響き渡ります。冷たい麦茶やかき氷に、思わず「助けられてるなあ」と思う日々。陽射しは強く、湿度も高く、毎年この時期は体力との対話のようです。
近ごろは「猛暑日」が当たり前になり、気温だけでなく“暑さの質”も変わってきたように感じます。かつての夏とは違い、体調管理が命にかかわる大切なことに。エアコンの使用や水分補給は、もう「がまんするもの」ではなく、「ちゃんと使うべきもの」へと変わってきました。
それでも、季節は少しずつ動いています。立秋が近づくこの頃、ふとした風に、夏の終わりの気配がまぎれていることも。たとえ暑さが続いていても、季節はちゃんと次の扉をノックしているのです。
二十四節気(にじゅうしせっき)は、太陽の動きに基づいた中国起源の暦です。
1年を24等分し、各節気は約15日間隔で巡ります。節気には、気候の特徴や農作業の目安が示され、自然のリズムを感じながら生活をする知恵が伝わっています。
大暑の期間に含まれる七十二候とは?
大暑の期間には、「七十二候(しちじゅうにこう)」と呼ばれる、小さな季節の区切りが三つあります。
七十二候とは、二十四節気をさらに細かく分けた暦のこと。自然の変化を繊細にとらえ、「草が芽吹くころ」「虫が鳴きはじめるころ」など、名前のひとつひとつに、季節の息づかいが込められています。
大暑のころの三候にも、夏の強さと、その奥にある命の営みが、そっと映し出されています。
- 初候:桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)
──桐の花が、実をむすびはじめるころ- 期間:7月23日頃~7月27日頃
- 意味:春に咲いた桐の花が、静かに実を結びはじめます。空の高みでそっと季節を告げるように、葉の陰に、小さな生命の形が宿っていく。夏の盛りのなかにも、次の季節の準備が始まっていることに、はっと気づかされます。
- 次候:土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)
──大地が湿り、蒸し暑さが増すころ- 期間:7月28日頃~8月1日頃
- 意味:強い日差しのあとに降る夕立。濡れた土のにおいが立ちのぼり、空気は熱を含んだまま動かない。肌にまとわりつくような湿気の中、蝉たちの声だけが、夏の力をそのまま体現しているようです。
- 末候:大雨時行(たいうときどきふる)
──大粒の雨が、時おり激しく降るころ- 期間:8月2日頃~8月7日頃
- 意味:まるで空に穴があいたように、突然の大粒の雨が降っては、あっという間に止む。その繰り返しの中に、夏の空の気まぐれさと、自然のエネルギーが詰まっています。乾いたアスファルトに、雨のしずくがまるを描く、その一瞬が、なんだか美しくて目を奪われます。
七十二候は、季節のほんのわずかな変化をことばにした、日本ならではの美しい暦。自然のリズムにそっと耳をすませるような文化です。虫の声、風の匂い、空の色──そんな日々のなかに、小さな季節の訪れを見つける楽しみがあります。
もっとくわしく知りたい方は、こちらの記事もどうぞ。
日本の豊かな文化を物語る、雨の呼び名
大暑のころは、ただ暑いだけでなく、雨の気配もちらほらと顔をのぞかせます。湿気をまとった風、突然の夕立、空のむこうに積乱雲──そんな夏らしい雨模様が広がる時期です。
雨といえば、日本にはたくさんの「雨の名前」があるのをご存じでしょうか。
その数、なんと400種類以上。細やかな自然の変化に名前をつけてきた日本人の感性は、本当に奥ゆかしいなあと感じます。
たとえば「秋霖(しゅうりん)」──これは秋の長雨を表す言葉ですが、もし日常会話でふっと使えたらちょっと素敵ですよね。「秋霖だね、今年のお米は大丈夫かしら」なんて、風景の中に心を添えるようなひとことです。
さすがにすべてを覚えるのは難しいですが、季節に寄り添った言葉をほんの少し知っているだけでも、日々が少しだけ豊かに感じられる気がします。ここでは、そんな「雨の呼び名」の中から、大暑の時期にぴったりのものをいくつかご紹介します。
日本には、四季折々の美しい自然と密接に結びついた雨の呼び名が数多く存在します。これらの名前は、それぞれの季節の風情や情景を繊細に表現していて、日本の豊かな文化を物語っています。
春、夏、秋、冬、それぞれの季節に特有の風情ある雨の呼び名をいくつかご紹介します。
春の雨
- 花散らしの雨(はなちらしのあめ)
- 桜が散る頃に降る雨。桜の花びらを散らすように降る雨。
- 菜種梅雨(なたねづゆ)
- 菜の花が咲く頃に降る長雨のこと。春の風物詩の一つですね。
- 春雨(はるさめ)
- 春にしとしとと降る雨。優しく降る雨で、春の訪れを感じさせます。
- 催花雨(さいかう)
- 花の咲く時季に降る雨。花を咲かせるための雨とも言われます。
夏の雨
- 夕立(ゆうだち)
- 夏の夕方に急に降り出し、短時間で止む激しい雨。夏の風物詩です。
- 篠突く雨(しのつくあめ)
- 激しく降る雨のこと。竹の篠が突き立つような激しい雨を意味します。
- 狐の嫁入り(きつねのよめいり)
- 晴れているのに降る雨。夏によく見られる現象で、不思議な光景を表現しています。狐を雨の名前の中に使うなんて、日本らしいですよね。
- 白雨(はくう)
- 短時間に激しく降る夏の雨。雷を伴うことも多く、スコールのような雨です。
秋の雨
- 時雨(しぐれ)
- 秋から初冬にかけて、短時間に降ったり止んだりする雨。風情があります。
- 秋霖(しゅうりん)
- 秋の長雨。収穫の時期に降る雨として、農作物に影響を与えることもある、ちょっとありがたくない雨。
- 紅葉雨(もみじあめ)
- 紅葉の時期に降る雨。紅葉した葉が雨に濡れて、一層美しく見えます。
- 山茶花梅雨(さざんかつゆ)
- 山茶花の咲く頃に降る長雨。秋から初冬にかけての雨を指します。
冬の雨
- 氷雨(ひさめ)
- 氷のように冷たい冬の雨。曲のタイトルにもなっています。
- 小糠雨(こぬかあめ)
- 細かくしとしとと降る雨。こちらは、歌詞の中に登場します。冬の冷たさを伴う静かな雨です。なぜか、冬の雨は歌詞の1シーンに登場することが多いですね。
- 秋雨(しゅうう)
- 秋に降る長雨。特に9月から10月にかけて見られる雨。秋の季節風や台風の影響によりことが多く弱く長く続く雨です。夏の暑さを和らげ、秋の深まりを感じさせるものですが、気温も下がるため、稲作農家にとっては注意が必要な雨です。
- 冬霧雨(ふゆぎりさめ)
- 冬の霧とともに降る雨。視界が悪くなることも多く、静かに降り続けます。
日本にはこれ以外にも、四季折々に様々な名前を持つ雨があります。
これらの雨の名前を読むだけでも、それぞれの季節の風情や自然の情景が浮かんできませんか?
わたしは、こういった日本の言葉が大好きです。言葉ひとつで、その情景が浮かんでくる言葉の数々。日本語って素敵ですよね。どんどん使っていきたいです。
大暑といえば、うなぎ──土用の丑の日とうなぎの話
大暑がやってくると、日本の夏らしさがぐっと色濃くなってきます。蝉の声が朝から響き、街では打ち水や日傘の風景が広がって、夏の空気が本格的に動き出すころ。そんな中、毎年楽しみにしている人も多いのが「土用の丑の日」、そして、うなぎの登場です。
2025年の「土用の丑の日」は、7月19日(土)と7月31日(木)。
年によっては2回めぐってくるこの日は、「夏バテ予防にうなぎを」という習慣が根づいた日でもあります。江戸時代後期、平賀源内が知人の鰻屋に頼まれて「丑の日にうなぎを食べると暑気あたりしない」と広めたのがはじまりと言われていますが、いまも昔も、うなぎは日本人にとって“元気の源”のような存在です。
また、この日はうなぎだけでなく、“黒い食べ物”をとるとよいとも言われています。これは「丑」=「黒」の象意からきていて、方角の守護神「玄武(げんぶ)」が象徴する色でもあります。黒豆、黒ごま、黒きくらげ──身近なものに、少し意識して黒を取り入れてみると、体の中から季節のバランスがととのうかもしれません。
暑さが極まるこの時期、ほんの少し意識を向けるだけで、食事が整い、心も整う。そんな“季節とつながる一日”として、土用の丑の日を過ごしてみてはいかがでしょうか。
まとめ|大暑、そしてその先へ
いかがでしたか? 大暑は、一年でもっとも暑さが厳しくなるころ。それでも、風鈴の音や打ち水の風景、うなぎや黒豆といった夏の味覚が、季節を豊かに彩ってくれます。涼をとる工夫や、体にやさしい食事を意識しながら、無理せず、夏とうまくつきあっていけたらいいですね。
大暑を過ぎると、空が少しずつ高くなり、ほんのり秋の気配がまぎれてくる……はずなのですが、今年は、なかなか秋が顔を見せてくれません。まだしばらくは暑さと寄り添う日が続きそうです。
次回は「立秋(りっしゅう)」について。暦のうえではもう秋──そんな季節の入り口をご案内します。